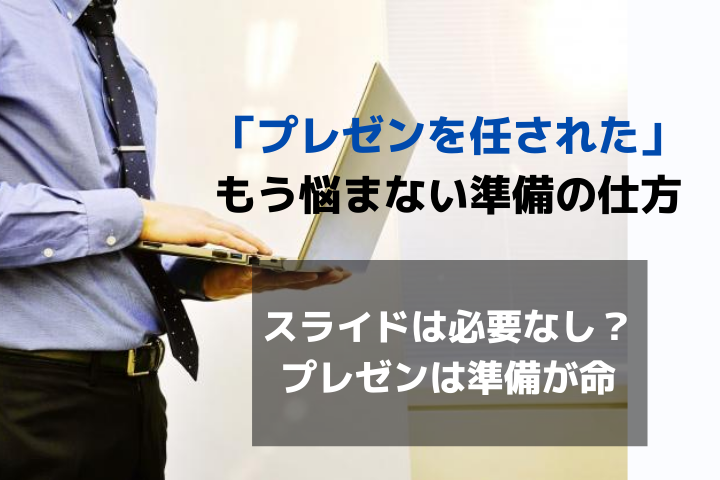

この記事はこんな方に向けて書きました!

あらゆる場面で活用できるプレゼンのコツは「スライド資料を作る前に原稿を作り込むこと」です。
あれ、以外に大したことじゃないなと思われたかもしれません。
でも、ご自身の経験や他の人のことを思い出してみてください。
多くの人はスライドを作り込むことからはじめているのではないでしょうか。
なぜ原稿を先に作り込むのか、理由は2つあります。
以下で詳しく解説します!
プレゼンがわかりにくくなってしまう大きな原因は、余計な情報がたくさん詰め込まれていることです。
プレゼンをする側は聞いている人に色々と伝えたくて細かい情報までプレゼンに盛り込んでしまいがちです。
しかし、聞いている人たちは数分から数十分で話を聞かなくてはならないので、細かいことを色々言われても理解できません。
そのため細かいことは全部削って本当に伝えたいことを伝える意識がとても重要です。
原稿はスライドに比べて修正がしやすいです。
そのため先に原稿を作り上げると余計な情報を削りやすいです。
また、原稿のほうがアウトラインの作成がラクです。
一般的に話すときの理想は1分間に400文字以下だと言われています。
これを守っていれば、余計な情報を削ったり、早口にならなかったりメリットが大きいです。
原稿作成のポイントとしては、始めからしっかり原稿を作り込まずに大枠(見出し)から作成することです。
見出しから作成すると大まかな流れが決まるので、言いたいことがわかりやすい原稿になります。
また、文章としてわかりやすいと言われているセオリーは守るようにしましょう。
例えば、概論を述べたあとに各論に移るなどです。
プレゼンの一番の主役はスライドではなくプレゼンターです。
すなわちプレゼンでいちばん重要なのは話し手の「しゃべり」です。
話す人がしっかり話して伝えることができれば、スライドがなくても問題ありません。
逆に言えばスライドや資料がどんなにしっかりできていてもプレゼンターの「しゃべり」が良くなければ伝わるものも伝わりません。
ではスライドはどのように活用すれば良いのでしょうか。
プレゼンは話し手の「しゃべり」を中心に構成します。
スライドはビジュアルサポートとして活用すべきです。
プレゼンターの言葉に加えて、図やグラフなどで視覚に訴えるとイメージが膨らみやすくなります。
スライド作成に関して留意すべきことがあります。
スライドにあれこれ文章を書いてしまうと聞き手の集中を妨害してしまいます。
人は文章を読むことと話を聞くことを同時に行うことは得意ではないです。
何度も言うようにプレゼンの主役は話し手なので、常に自分のしゃべりに意識を集中させるように考えましょう。
「マーケティングのグル」と呼ばれる著名なマーケッター、セス・ゴーディン氏は「1枚のスライドに6語以上は入れるな」とアドバイスしています。
アップルの創業者、スティーブ・ジョブズのプレゼンを見てもスライドはシンブルで視覚に訴えるものになっています。

しゅんてぃー
プレゼンターのしゃべりと視覚に訴えるスライドが重要だとよくわかります!

しゅんてぃー
プレゼンのインプットを増やしたい方はTEDがおすすめです!
