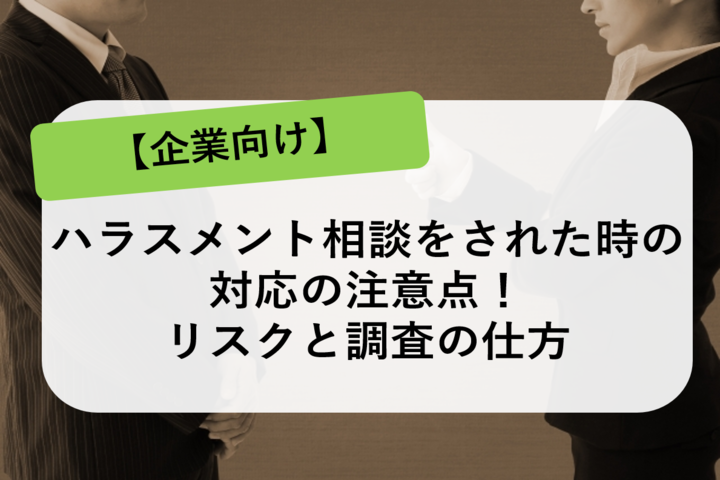
近年、種類が増えてきた「ハラスメント行為」。
今回は、企業としての対応のポイントを紹介します。
このページを相談者(被害者)の方が見る場合は、企業が対応していない場合に請求できるポイントになりますよ。
参考になれば幸いです。
このページの目次

ハラスメントとは、職場やプライベートに限らず、相手の意に反する行為で、嫌がらせや不快になる行為をすること。または強要する行為のことです。
最近では、lineなど職場時間外でのしつこいハラスメントも対象になりつつありますが、内容によりますので一概にはいえません。
ハラスメント行為と判断されるのは、実はあいまいで、受けている人が「ハラスメントをされた」と感じたら、ハラスメントと認定されます。

職場で上司からされた場合等、波風立てないために我慢したり、表情に出さないことも多く、行為を行った人側からは「そんなつもりではなかった」「嫌そうにはみえなかった」など、お互いの認識の差が生まれやすいのも特徴です。

ハラスメントを放置すると企業としてリスクを負うことになります。また人権問題としても、企業はハラスメント報告を受けたらすぐに対応することが必須です。
社内でなぁなぁに終わらせた(この時点で違法)としても、被害者は外部機関の相談窓口や、弁護士を雇うことも可能です。
仕事ハラスメントがおこなわれ、証明された場合、企業は「債務不履行責任」「不法行為責任」などの「法的責任」が求められます。さらに被害者が被った精神的なダメージによる損害を、企業は賠償しなければなりません。

みやりーん
民事訴訟を起こされたとなっては、企業のイメージダウンなどリスクは大きいですね。
中途半端な対応の場合、昔よりもSNSが発達した現在では、すぐに悪い噂が広がる可能性があります。
最悪な場合は、実際の事実よりも尾ひれがつき、事がおおきくなったような内容で広がる場合もあり。
各ソーシャルメディアで追跡できる場合もありますが、もしも火消しを行う場合、多大な時間を費用がかかります。
ひとりの人がハラスメントで声を上げた時点で、環境的にハラスメントを生みやすい環境だった場合や、勇気をもらったとして他の方がさらに相談する場合や、離職者が増える可能性もあります。

企業としては、ハラスメントは人権問題に直結しているため、必ず対応することが必須です。
企業にとっても、相談者にとっても、証拠として扱われます。
ポイントは、最初の相談から始まっている点です。メールで相談受けた場合、返信があまりにも遅かった場合は「企業として誠実ではない」と判断されることもあります。
また窓口相談で、相談員が軽い感じで聞いている(ように見えただけで)「真剣にとりあってくれなかった」という印象の証拠として取られます。
(実際そのことで、どうジャッジされるかは証拠案件などの兼ね合いになり異なります。)

みやりーん
つまり、被害者にとっては、加害者との被害の証拠だけでなく、その相談をした企業の対応の誠実さなども、証拠となるのです。
「加害者が勝手に起こしただけなのに」と思うかもしれませんが、その加害者が従業員である以上、会社としても改善義務があるため相談対応が見られるんですよ。
ハラスメントは「人権問題」のため、企業の対応がしっかり観察されます。
相談してきた被害者により発覚するのですが、ボイスレコーダーのようなハッキリした証拠がない場合は、100%鵜呑みにするのも危険です。証拠の程度を判断し、周りの方や加害者へのヒアリングも必要とされています。

みやりーん
とはいえ、加害者へヒアリングすることで被害者への影響も考慮して慎重にやる必要があります。
ヒアリングや調査をする場合は複数が望ましい
1.被害者のヒアリング
2.被害者の許可を得て関係者(第3者)をヒアリング
3.被害者の許可を得て加害者をヒアリング
4.意見の食い違うところを再度調査
5.被害者の虚偽の可能性がある動機がないか調査
6.他の被害者がいないか調査
7.処分の決定(処分の決定は、弁護士や法務部にに相談するのがよい)※のちに揉めない為
被害者への影響を考慮し、加害者への処分を決定、もしくは対応(注意喚起など)を行って下さい。
社内で解決することが一番ですが、内容に納得がいかないと、被害者が外部の機関(弁護士)などに相談し、会社側に対し、交渉(ですめばよいですが)や訴訟を起こす可能性もあります。

みやりーん
その際は、相談してきた時点からの会社の対応も含め見られていますので、慎重に!
相談してきたときからの対応だけでなく、日ごろから、注意喚起などの予防措置を行っているか等も見られます。
在職中に、相談者(被害者)が訴えた後に、(そのことが原因で)出社しなくなったり、退職したりしても、調査は続行する必要があります。
相談者(被害者)がもういいですと、調査打ち切りをしない限り。
ここで勝手に辞めてしまうと、「企業は誠実な対応をしなかった」という証拠として残されます。
対応のすべてが調査されているため、できるだけ書面など文言化して残しておくことがよいです。
近年ハラスメントの幅が広くなってきており、企業に勤めている人だけでなく、内定者などにも対応されるケースがあります。
また、セクハラでも女性から男性へ行われたパターンもあり、「性別」「年齢」「雇用形態」などにかかわらず、その企業に従事している人(従事する内定者を含む)が対象となります。

ただ、両社の場合、派遣元にまずは相談している場合が多いので、派遣元に営業からのクレームや相談という形、発覚することが多いでしょう。そのあとの対応は社員と同じようにみられている(証拠にされる)ので誠意かつ迅速に対応しましょう
すべて就業規則に盛り込むだけでなく、日ごろからの注意喚起や、講習会を行うことが大事です。これらを行っていれば、「企業としての努力や対応あり」と判断されやすいです。
忘年会シーズンなど、会社側から注意喚起が必要です。
最近では、就業規則の中に、アルハラやセクハラなど起こした場合、解雇処分などの規約がある企業も多いですね。
とはいえ、忘年会などのシーズン前に、会社側としてひとこと注意喚起を促していると、「企業は対応を行っていた」と判断されます。
ある企業では、定期的に、セクハラやパワハラの認識講習会を行っている企業もあります。
Excelも使えないんですか?」などITにうとい年配の方へ若い方が言う場合が多い。
企業としては社内でのスキル講習会などを開くことで対応しています。
早く終われハラスメント。
主に就活の内定者に対しておこなれるハラスメント。企業採用において、自社に来てほしいがために、他社への就職活動を早く終わるように促したり、「内定を取り消す」旨を匂わせたりするハラスメント。
あまりに返事の催促がはやかったりすると、オワハラと感じるようで、初めから期限を決めるなど対応が必要です。
納得のいく形で就職しないと、結局、離職につながりやすい場合もありますので、お互いのメリットを考えてもオワハラは良い結果はうみません。
性別や年齢・雇用形態・内定者等、組織に関わる人すべてが対象
ハラスメントの相談を受けたら、「誠実」「迅速」に対応することが大事です。
参考になれば幸いです。
【あわせて読みたい】ハラスメントの詳しい種類はこちら

こんにちは。「みやりーん」と、申します!
転職・派遣の人材業界で、渉外・マーケティング・制作等、マルチに戦うWEBディレクター。アルバイト、派遣、契約社員、正社員をひととおり経験。7人材業界の裏側や仕組み、おすすめの派遣会社、働き方について発信しています。
特に、派遣については「常駐先側の気持ち」「派遣元のおもわく」「求職者の選び方のポイント」「サイトの仕組み」など詳しくご紹介!
働き方改革の一環で、副業として掛け持ちができるお仕事や、転職の際の注意点などもまとめていますよ!
よりよい選択のヒントになれば幸いです。Twitter

はじめまして! 現在、中途・派遣それぞれの転職領域にて就業中。渉外・マーケ・制作とマルチに戦うWEBディレクター!
アルバイト・派遣、契約社員、正社員の雇用形態を経験。採用側、サイト運営側、利用者側それぞれの経験から、人材業界の採用やサイトの仕組みの裏側などを話しちゃいます!「働き方改革」のヒントも紹介!